
自社DXの知見を新規事業へ活用 ~建材メーカーの新しい挑戦~
提供:株式会社シマブン
株式会社シマブンはグレーチングをはじめとしたユニバーサルデザイン商品・環境関連商品の企画・開発・製造を営みながら、自社のDX推進をヒントに新たな事業を立ち上げられました。社長である島さん、事業企画・マーケティング グループ グループ長 兼 広報・事業企画担当の濱さん、事業企画・マーケティング グループDX推進担当の金永さんの3名にインタビューをしてきました。
社内DX推進から新規事業開発へ
-
 中島/SISC
中島/SISC
当センターにお越しいただいた時の最初のご相談が、2021年11月頃でしたね。確かその時の主なテーマは倉庫管理やRFIDに関する相談だったと記憶しています。
-
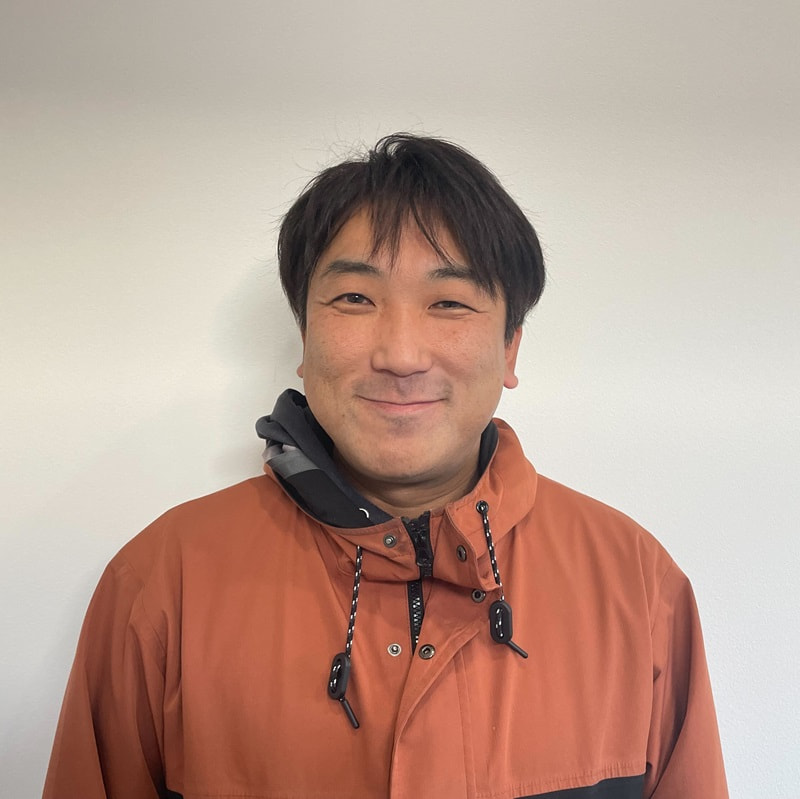 濱さん
濱さん
そうですね。自社のDXを進める上で、倉庫管理のシステム化について相談させていただきました。いろいろなサポーティングカンパニーさんとの面談を通じて、具体的な方向性を模索する形でスタートしましたね。
-
 中島/SISC
中島/SISC
記録を確認すると、かなり多くの企業が相談説明会に参加していました。さらに、個別面談にも5〜6社ほどお越しいただいていましたが、そこから得られたものはありましたか?
※相談説明会:複数のサポートカンパニーに対して相談内容を説明する機会を設けるスマート化センターのマッチング機能の一つ
※個別面談:相談説明会参加企業の中から、解決ソリューションやサービスを提示できる企業を選び、個別に面談を実施する
-
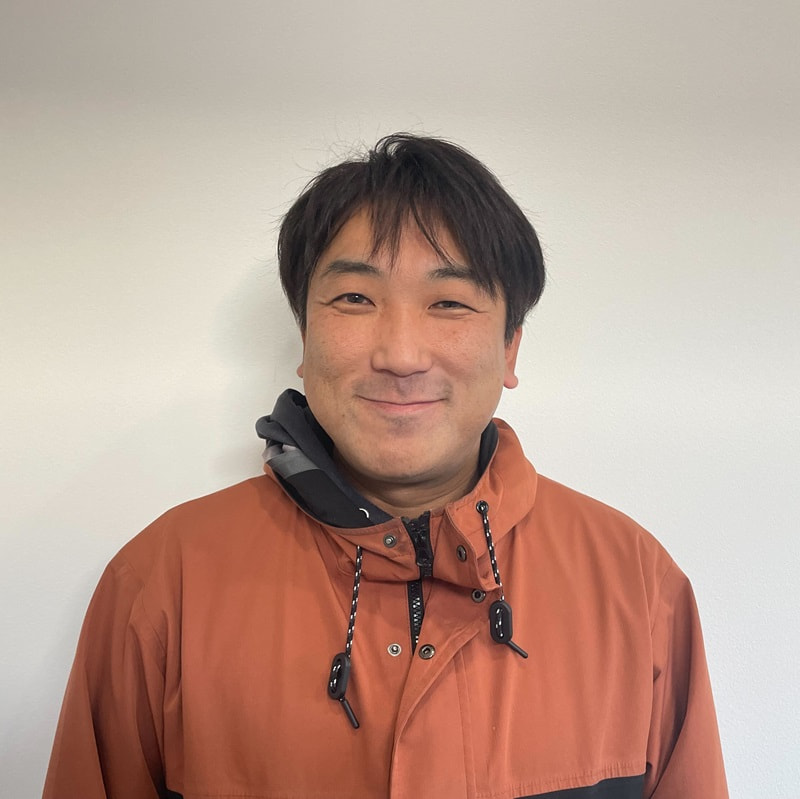 濱さん
濱さん
そうですね、スマート化センターさんを通じて複数のサポートカンパニーと繋がり、ご縁をいただけたのは大きな成果でした。先日開催された展示会でも、以前お世話になった企業の方々にお会いし、改めてご挨拶させていただきました。今後も関係性を続けていきたいと思える企業さんが何社かいらっしゃいます。また、スマート化センターさんが配信しているメルマガのセミナー情報も非常にありがたいです。たくさんの情報やアドバイスを得ることができています。
-
 中島/SISC
中島/SISC
いつもご覧いただきありがとうございます!
当時は相談者としてスマート化センターをご利用いただきましたが、その後新規事業を立ち上げ、現在ではサポーティングカンパニーとして登録され、支援側としても関わってくださってますね。建材メーカーという枠にとどまらず、新規事業にチャレンジしようと考えたきっかけや経緯を教えていただけますか?
-
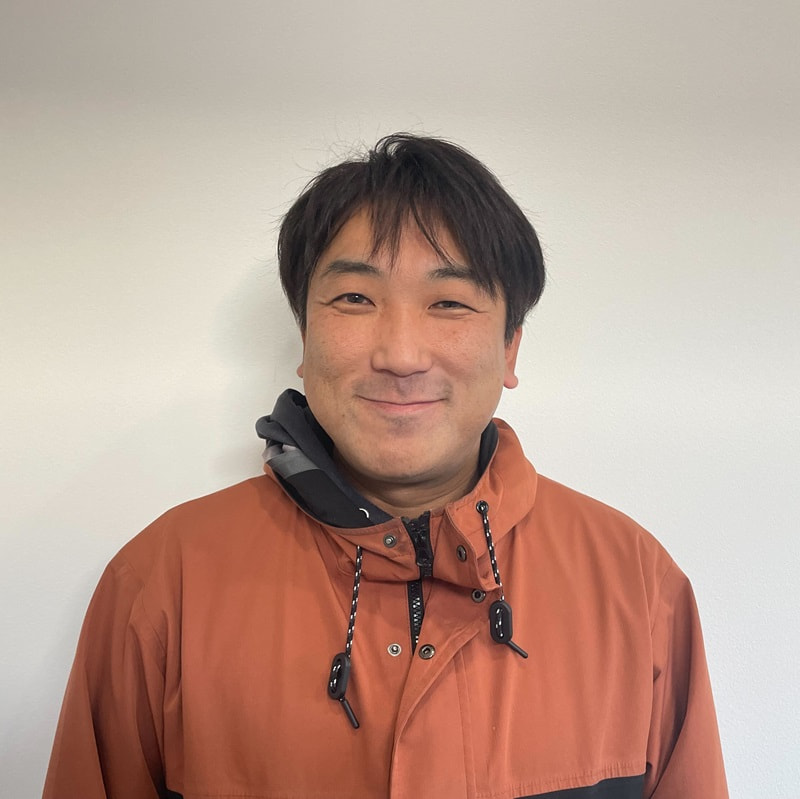 濱さん
濱さん
私自身、入社当時は「建材メーカー」というイメージを持っていましたが、実際に業務に携わると、会社がさまざまな事業を展開していることに驚きました。建材事業が軸となるからこそ可能な取り組みがあるのですが、何より社長が「こういうことに挑戦してみよう」「ああいうこともやってみよう」と積極的に新しいアイデアを推進し、地域貢献への思いを強く持っていたのが印象的でした。
その新しい挑戦の一つが、たまたま今回のDX(デジタルトランスフォーメーション)だったというわけです。社長が他社の経営者の方々との集まりでDXの話題に触れた際、弊社のDXへの取り組みが他社と比べて比較的早い段階で進んでいたことがわかりました。例えばクラウドシステムの導入やUTM(統合脅威管理)の実装などが挙げられます。その結果、他社から相談を受ける機会が増え、「地域に貢献する」という理念の延長線上で、新事業としてサポート活動を旗揚げすることになりました。そして、そのタイミングで金永が入社し、新事業のスタッフとして本格的に始動した形です。
-
 中島/SISC
中島/SISC
なるほど。自社でのDX推進から得た知見を活かして、困っている方々を支援しようという考えに至ったのですね。
地域企業を支えるシステムアドバイザーの取り組み
-
 中島/SISC
中島/SISC
金永さんが行っている新しいサービスは顧客のどのような問題を解決しますか?
-
 金永さん
金永さん
機器を導入する際に、付き合いのあるメーカーや営業さんから提案されたものをそのまま採用していてスペックがあっていなかったり、無駄な出費をしてしまっているという会社さんが多いんです。
じつは弊社もそうで、もともとのきっかけはセキュリティ機器の見直しでした。営業さんから提案いただいたものをそのまま導入していたのですが、私が設定をチェックしたところ、8つある機能のうち7つがオフに設定されていたんです。その状態では、セキュリティとしての役割を果たせませんよね。後からわかったことですが、通信速度が遅いという理由でほとんどの機能をオフにしてしまっていたのです。セキュリティがしっかりしていても通信速度が遅くて仕事にならない、というのは本末転倒です。そこで、「必要な機能をしっかり活用できる、性能の良いUTM(統合脅威管理)を入れましょう」と提案し、現在は安定して運用できています。こうした改善を進める中で、社内の他のシステムも見直してみると、高性能なものを必要以上に導入していたり、リース契約が過剰に積み重なっていたりするケースが多かったんです。「提案されたから導入した」という理由だけで、結果的に無駄な投資をしてしまう中小企業さんが少なくありません。
多くの中小企業では、IT専任の担当者がいないため、こうした問題に気づきにくいです。その結果、事業継続を目的とした投資のはずが、かえってコストばかりがかかる状況になっていることがあります。私はこうした企業さまのお役に立ちたいと考えており、特に、UTMの見直しをきっかけに、その他のシステムも再検討し、適切な運用を目指す提案をしています。
また、定期的にお客様の元を訪問して「誰に聞いたらいいかわからない」といったお悩みに応えることで、企業さまの負担を少しでも軽減し、本業に専念できる環境作りをサポートしています。
-
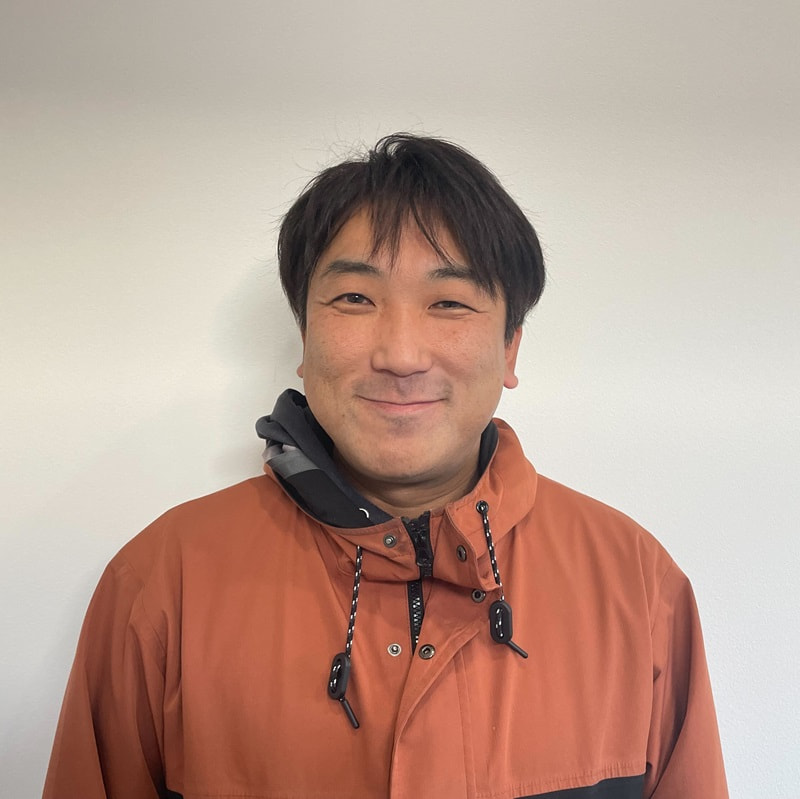 濱さん
濱さん
地域の企業のみなさんのお困りごとを解決するサービスです。「御社のシステムアドバイザーやIT担当者になります」とお伝えしています。
地域貢献と挑戦への原動力
-
 中島/SISC
中島/SISC
もともと社長が色々と新しいことに取り組まれているというお話がありましたが、それは社長ご自身の性格や生い立ちが関係しているのでしょうか?
-
 島社長
島社長
そうですね、うちの祖父や父も同じような姿勢だったと聞いています。祖父は、お客様が困っている姿を見ると、「じゃあこういうものを創ったらどうだろう?」とアイデアを出し、環境改善のための製品を作ったりしていたようです。父もそういうことが好きで、お客様の困りごとを解決していました。私自身も、困っている人を支援することを重視しています。いわゆるユニバーサルデザインの考え方で、それが地域のためにもなると信じています。
ある時、県の職員さんと話していて、気づかされたことがありました。その方は、「地域に雇用を生み、人が定着することで、人口減少を防ぐ。さらに、税収を確保するためにも地元企業に頑張ってもらう必要がある」と仰っていました。
その話を聞いて、「目的は私たちも同じだ」と思いました。我々も地域のために働ける場を作り、人々が収入を得られるようにすることが大事です。そうしないと、企業自体も存続できません。地域に人がいなくなれば、企業も滅んでしまいます。
また、税収がなければ社会資本の整備も進まず、子どもたちの未来にも悪影響が出てしまいます。だからこそ、地域にないものを中央や海外から取り入れたり、地方で生み出した良いものを積極的に外へ売り出して利益を上げ、納税するというサイクルを回さなければなりません。
どんどんチャレンジをし続ける理由はここにあります。地域に留まるだけでは、新しいものは生み出せませんし、情報の流れも遅い。それではいけないので、我々は常に新しい情報を取り入れ、積極的に挑戦して、「こんな田舎にもすごい会社がある」と思われるような存在になろうと考えています。
新しい挑戦に対する心構え
-
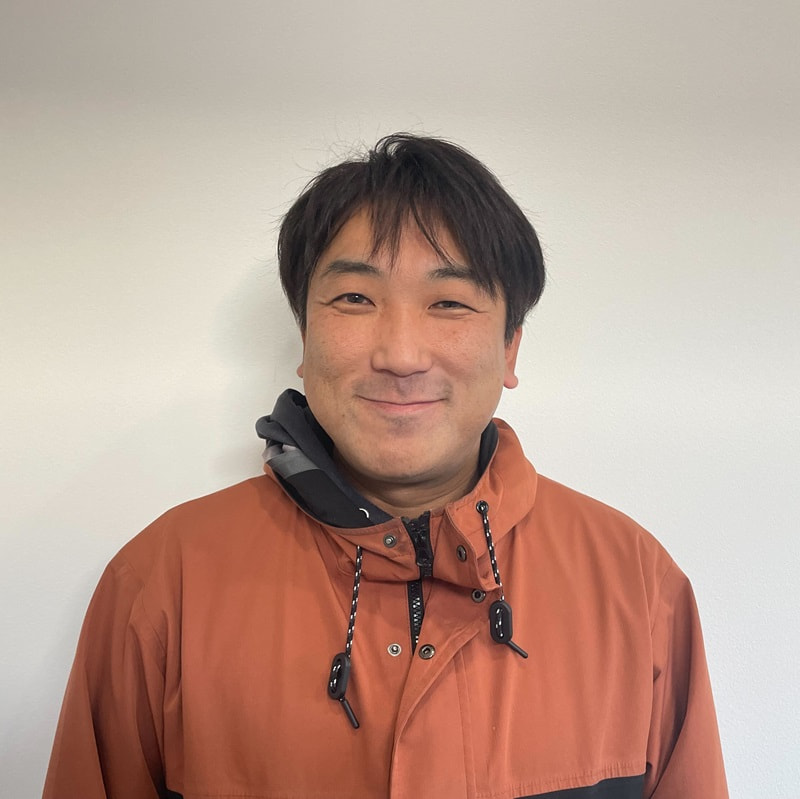 濱さん
濱さん
社長は、「これ、今社内でやっていないけどできるかな?」とか、「これをやると営業のサポートになると思うけど、どう?」と、提案ベースで聞いてくださるんです。「やりなさい」と命令されるわけではなく、「できる?」と聞かれるので、自然と「それはできません」とは言えないですよね(笑)。私自身も初めてのことばかりですが、「じゃあやってみてもいいですか?」という形で進めることが多いです。
そうやって試行錯誤して取り組んだ結果、うまくいくと「じゃあ次はこれをお願い」と新しい課題をいただける。どんどん提案したことが形になっていく感覚がありました。
-
 中島/SISC
中島/SISC
新しいことにチャレンジするには勇気が必要ですよね。「やってみないとわからない」という考え方も、非常に重要なキーワードだと感じます。新しいことに挑戦すれば何とか形になることもあれば、逆に挑戦しなければ何も始まらない。そのような前向きなマインドを持っていることが素晴らしいと思います。
-
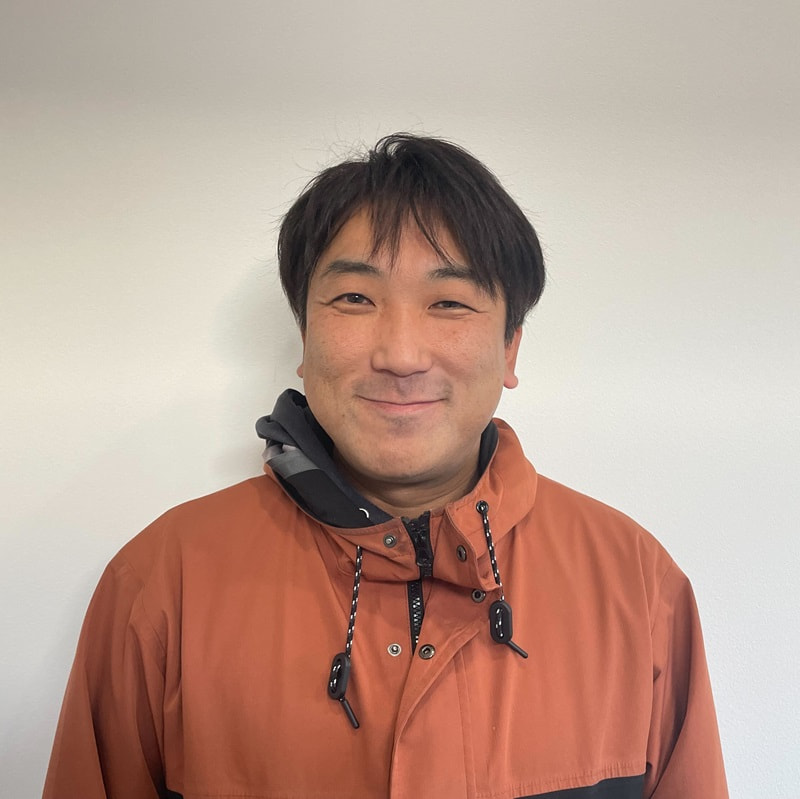 濱さん
濱さん
そうですね。失敗しても決して怒られません。失敗した時は「なぜ失敗したのか」「次にどう繋げるか」を考え、理解していれば、「頑張ったね」と声をかけてもらえる。私は失敗しても怒られた経験がありません。それどころか、「じゃあ次はこうしてみたら?」と具体的なアドバイスをいただけるんです。そういった環境があるからこそ、次の挑戦にも気軽に取り組めるんだと思います。ただ、もちろん失敗を目的にしているわけではありませんけどね(笑)。
-
 中島/SISC
中島/SISC
そのような環境があるからこそ、みなさん前向きに挑戦し、自ら進んで行動できるのだと思います。
-
 島社長
島社長
それは、彼ら自身がその環境を理解し、受け入れる心構えを持っているからだと思います。この心構えがないと、なかなかその流れに入れないかもしれません。ありがたいことに、多くのスタッフがその心構えを持っている。それが挑戦のサイクルを回しているのだと思います。それは間違いないですね。
-
 中島/SISC
中島/SISC
その心構えはみなさん最初から持ち合わせていたものですか?例えば、社長が新しいことを提案された時に、「私がやるんですか」というような反発は今まで一度もありませんでしたか?
-
 島社長
島社長
ああ、それは過去に何度もありましたよ。こちらが「こうやってやろうよ」と伝えても、「いや、今は忙しいです」と言って動かない人もいました。やっぱり行動が伴わないと業績にも影響が出ますよね。その結果、以前は感情的になって怒ってしまうこともありました。もちろん怒るのは良くないことだと分かっていたんですが……。
-
 中島/SISC
中島/SISC
そこから、社長のマインドが変わった理由は何だったんでしょうか?
-
 島社長
島社長
それは、やっぱり失敗を重ねる中で学んだ部分が大きいと思いますね。怒ったところで何もいいことはない、と実感しました。それに、長男が会社に入社したことも影響があると思います。妻や社員からも「もっとこうしたらいい」といったアドバイスをもらい続けて、最初は耳に入らなかったのが、年齢を重ねるうちに少しずつ受け入れられるようになっていったんだと思います。正直、明確なきっかけがあったというより、自然にそうなった感じです。具体的に何が転機だったかは、あまり覚えていないんですよね。
-
 中島/SISC
中島/SISC
実は他の会社の社長さんからも、似たようなお話を伺ったことがあります。以前はすごく怒りっぽかったけど、経営者同士の交流や勉強会、経営塾に参加するようになって、「自分が叱られる側になって気づかされた」とおっしゃっていました。それがきっかけで、社員と一緒に取り組む姿勢に変わったというお話でした。
-
 島社長
島社長
それは確かにありますね。経営塾や勉強会、仲間との出会い、さらには研修の影響も大きいです。そういった場を通じて学び、考え方が少しずつ変わっていったのだと思います。
情報収集のためのアンテナを立てておく
-
 中島/SISC
中島/SISC
新規事業を始めるにあたって、顧客のニーズや最新技術に関する情報を収集することはとても重要だと思いますが、どのように取り組んでいらっしゃいますか?
-
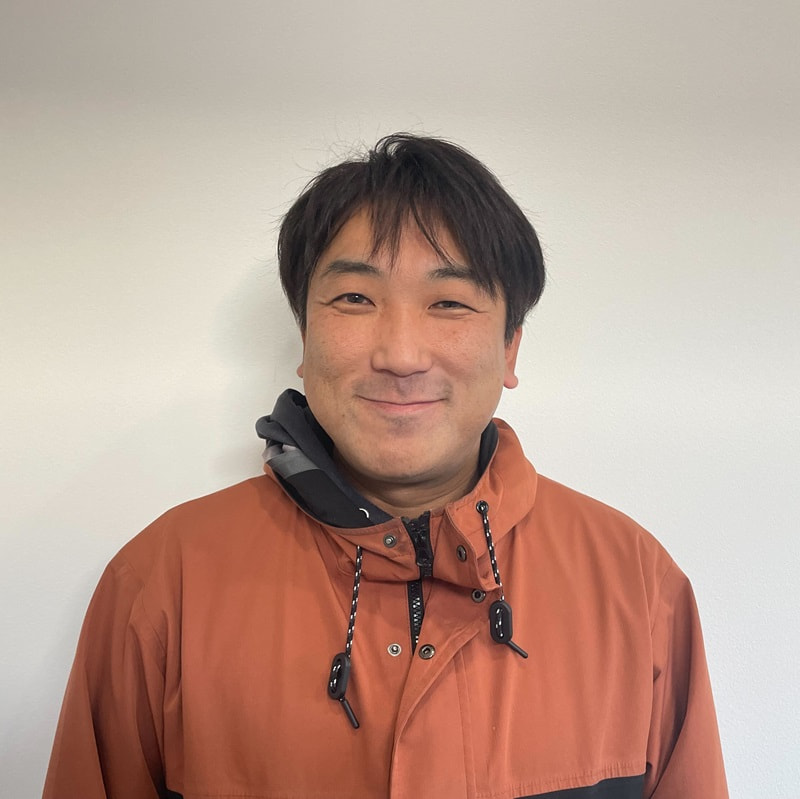 濱さん
濱さん
そうですね。例えば建材やITの展示会に頻繁に行くようにしています。最近では、建材の展示会にも建材だけでなく、DX関連の技術や、それに付随する新しい商品も出展されていることが多いんです。東京や大阪などに行くと、地方では知らない情報や技術に触れることができます。そこで得た情報を持ち帰り、「これを今の事業に活かせないか」「新しい事業として展開できないか」といった形で考えるようにしています。本当に常にアンテナを立てて情報収集をしています。展示会以外でも、普段どこかに出かけた際に目に入るものが気になってしまうのは職業病かもしれません(笑)。
-
 島社長
島社長
そうですね、この2人(濱さんと金永さん)は特に外に出て、いろんな方と話をする機会が多いですからね。私たちよりも頻繁に、様々な場所で情報収集をされていると思います。
-
 金永さん
金永さん
はい、いろんな社長さんや経営者とお会いすることが多いので、ネット上で調べる情報とはまた違った、生の情報を得ることができます。同じ悩みや課題を抱える方々と話すことで、その具体的な悩みを理解し、解決策を探ることも多いですね。その中で「世の中にまだないものを作る」という視点や、人々の困りごとにフォーカスする社長の考え方を改めて感じます。直接ヒアリングをするような形でニーズを把握するのがポイントですね。
それに加えて、例えば鉄鋼関係の組合や、その他の業界の勉強会などにも積極的に参加しています。こうした場での繋がりは非常に大事です。参加費や会費はかかりますが、それ以上の価値があると思っています。同じ会員同士で助け合えることも多いですし、自分たちの活動が他の会員の役に立つことで、さらに新しい繋がりや可能性が生まれることもあります。
-
 中島/SISC
中島/SISC
なるほど。確かに組合や勉強会の「役」を引き受けるのは大変だと感じる人も多いですが、どう思われますか?
-
 金永さん
金永さん
そういう役割を引き受けるのは、学びの場でもあるんです。深く関わることで、一生懸命な人たちが集まり、互いに応援し合う環境が生まれます。実際、そういう方々から助けてもらった経験もありますね。役を引き受けることで、自分自身も成長できますし、コミュニティ全体にも良い影響を与えられると思います。
志の高さが生む成長の連鎖
-
 中島/SISC
中島/SISC
濱さんと金永さんの志の高さが素晴らしいですね。お話を伺っていると、そういった志の高い方々が集まっている会社だという印象を受けます。
-
 島社長
島社長
そうですね。事務的に動く方ではなく、志を持った方々が集まっています。以前からいる従業員もその影響を受けていて、新しい風が社内に吹き込まれていますよ。さらに私の息子が会社に入ったことで、「この会社は存続していくんだ」と社員たちにも安心感が広がったんじゃないかと思います。社員の平均年齢がこの1年で30代後半まで下がり、今年も新卒2名が入社しました。長く勤めている方も多く、10年以上の社員も増えています。
-
 中島/SISC
中島/SISC
社内のチャレンジ精神やマインドセットは、どのように広めたり、受け継いでいらっしゃるんでしょうか?
-
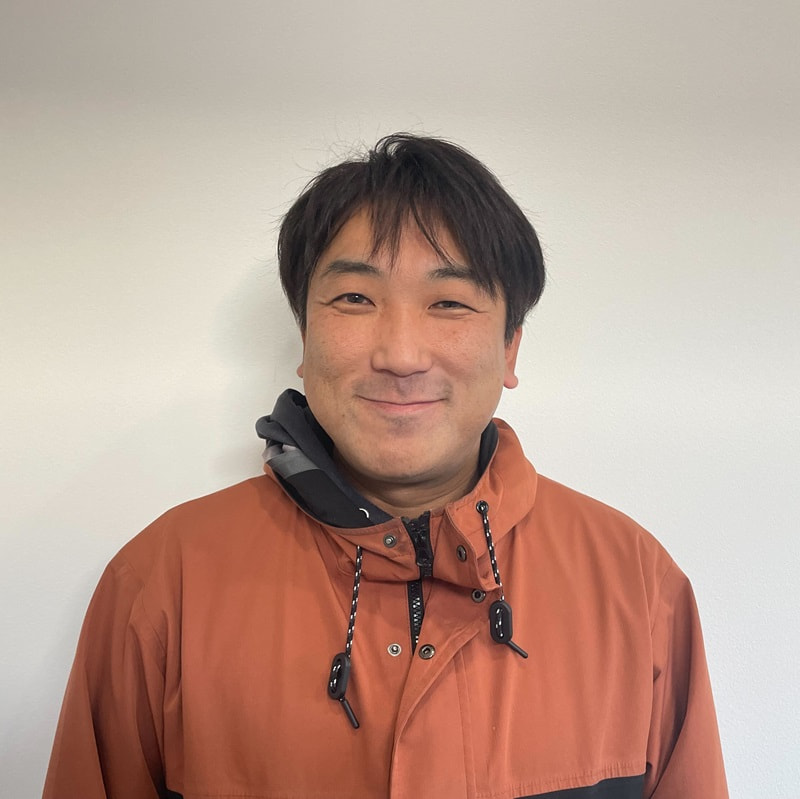 濱さん
濱さん
特別な研修は行っていないんですよね。僕が入社した頃は研修もあったんですが、今は面談や朝礼、勉強会を通じて自然に広まっている感じです。
-
 島社長
島社長
そうですね。日常的にミーティングも頻繁に行っていますし、そういう場を通じて伝わっているんじゃないでしょうか。
-
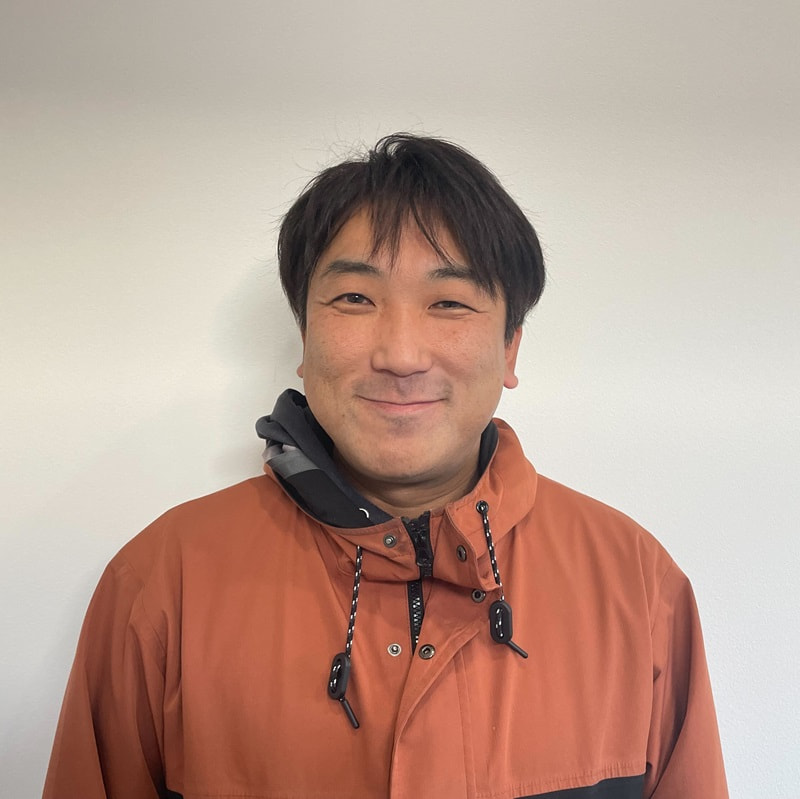 濱さん
濱さん
あと、他部署間の壁がほとんどないのも大きいと思います。製造業だと製造部と業務部が分断されているケースが多いですが、うちはそういうことがほとんどありません。物理的な作業場所が違うだけで、朝礼は部門を超えて混ざってやっています。そのおかげでコミュニケーションが非常に活発で、いざというときの連携もしやすいです。
-
 中島/SISC
中島/SISC
チームとして動いている感覚が強いのでしょうか。新規事業チームの在り方としてはどのような感じですか?
-
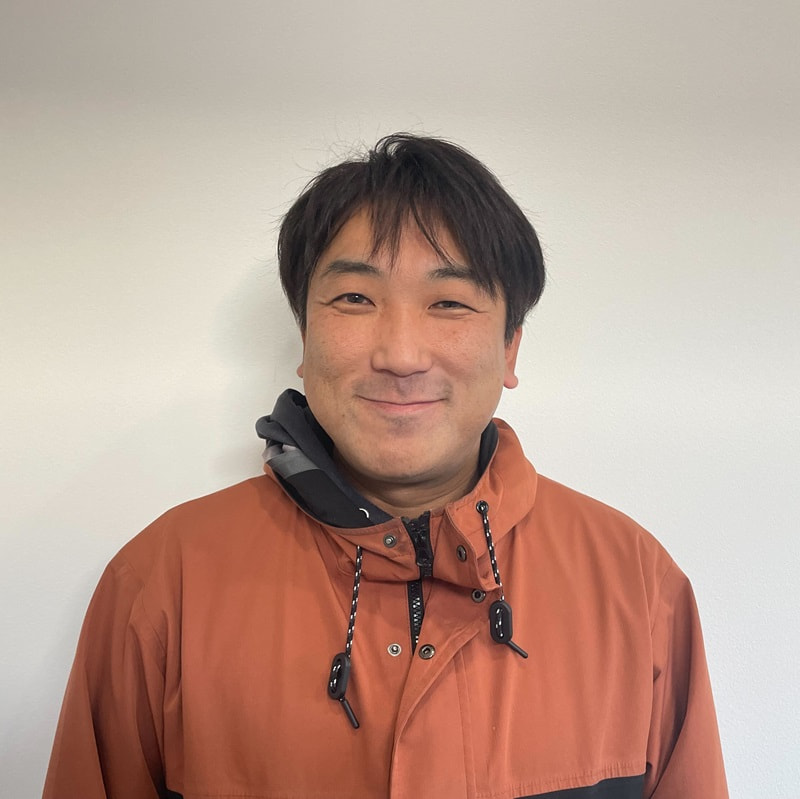 濱さん
濱さん
そうですね。うちのメンバーはそれぞれ優秀で、僕はサポート役に徹しています。みんなが主役で、僕は黒子ですね。部下とは言えないほど、全員すごいんですよ。毎朝のミーティングも効果的で、僕はいじられる側ですけど、それもまた一つのコミュニケーションです(笑)メンバーそれぞれのやり方があり、全てに正解はないと思います。ただ、僕のアドバイスを活かしてもらえた時や感謝される時が一番のご褒美ですね。
-
 中島/SISC
中島/SISC
「縁の下の力持ち」なんですね、素晴らしいリーダーシップだと思います。
-
 島社長
島社長
社内のDXも進んでいて、総務の女性が中心となり取り組んでいます。来年21歳になる若手の子なんですよ。「こんなに難しいとは」とくじけそうになったこともあるそうですが、今ではしっかり成果を出しています。
-
 金永さん
金永さん
そうやって言えるということは壁を乗り越えたということの証明ですからね。先日はまた別の子が展示会出展を通してすごく成長した姿を目の当たりにしました。若手が本当に頑張っているんですよね。
-
 島社長
島社長
濱さん、金永さんをはじめとする中堅メンバーがしっかり見守りながら、何か相談したら必ずアドバイスをしてくれるという環境が整っているからこそでしょうね。
-
 中島/SISC
中島/SISC
優秀な人材がたった1人いたところで会社全体を前に進めることはかないません。社内のDXと新規事業のどちらも前に進められているのは、人材が育つ素晴らしい環境をつくり、チームとして機能する状態になっているということが大きな要因のひとつなのかもしれませんね。
本日はお話を聞かせていただきありがとうございました。

